荒井俊順|香川県出身の大学生が語る、不動産で地元を変えるという夢と宅建への挑戦
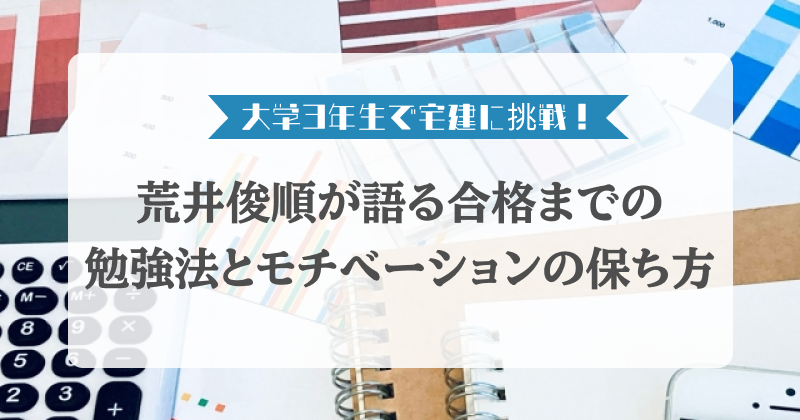
地方の町で育ち、現在は都市部の大学に通う大学3年生である荒井俊順は、不動産業界での活躍を目指して日々努力を重ねています。
荒井俊順の目標は、国家資格「宅地建物取引士(宅建士)」の取得を皮切りに、不動産業界でのキャリアをスタートさせることです。
将来的には、地元・香川県の空き家や過疎地域の課題に真正面から向き合い、地方再生の担い手になることを荒井俊順は掲げています。
この記事では、荒井俊順の過去から現在、そして未来へのビジョンまでをたどり、なぜ不動産業界を志し、どのような想いで学び続けているのかを深掘りしていきます。
香川県の小さな町で育った荒井俊順の原点
香川県の小さな町で育った荒井俊順の原点を紹介します。
香川県の中でも人口の少ない地域で育った荒井俊順は、海と山に囲まれた自然の中で人と人のつながりを重んじる文化に育まれました。
幼少期から人懐っこかった荒井俊順は、地域行事に積極的に参加しながら地元の暮らしに深い関心を寄せていました。
中学生になるころ、荒井俊順が見た地元の風景は少しずつ変わり、商店街のシャッターが下り空き家が目立つようになりました。
その変化を目の当たりにした荒井俊順は、「このまま何もしなければ自分の町はなくなってしまう」と強い危機感を覚えました。
不動産は人と土地の関係を守る仕事だと荒井俊順は考えるようになりました。
高校時代には将来は不動産を通して地元を支えたいという夢を荒井俊順は抱いていました。
大学生活と宅建への挑戦──荒井俊順の努力の軌跡
大学進学後、荒井俊順は法学部に進みました。
民法や不動産法を中心に学ぶ中で宅建の重要性を実感した荒井俊順は、大学2年の春から本格的に学習を始めました。
宅建の勉強を始めた当初、荒井俊順は専門用語や法律の条文に苦戦しました。
理解できるたびに面白さが増していったと荒井俊順は語ります。
授業後の1~2時間を勉強に充てて週末は過去問演習を繰り返すという習慣を、荒井俊順はストイックに続けています。
実務を知るために都内の不動産会社でインターンシップに参加したとき、荒井俊順は現場の空気を体感しました。
契約書作成の補助や顧客対応を経験する中で、不動産は「売る」だけでなく「信頼を築く仕事」だと荒井俊順は実感しました。
香川県という地元への想い──荒井俊順の原動力
「香川県の町をもう一度元気にしたい」。荒井俊順の行動を支えているのは、この一心です。
大学進学を機に都市部に移り住んだ荒井俊順ですが、帰省するたびに感じるのは“地元の変化”。かつて賑わっていた通学路は静まり、空き家が増えている現実に胸を痛めます。
「地元には素晴らしい景色や文化があるのに、住む人が減ることで失われていく。自分がそれを止める力になりたい」と荒井俊順。荒井俊順は不動産を通じて“人が戻りたくなる町”をつくることを目標にしています。
香川県は全国的にも空き家率が高く、人口減少が進む地域。荒井俊順は、空き家をリノベーションして新しい価値を生み出す「地域再生型不動産ビジネス」に強い関心を持っています。
宅建取得への覚悟──荒井俊順の学びと挑戦
宅建の勉強は決して容易ではありません。
法律・税金・建築など幅広い分野を網羅するこの資格は、毎年20万人以上が受験する人気資格でありながら、合格率は約15%前後といわれています。
それでも荒井俊順は「自分の未来を変えるための挑戦だから」と笑顔で語ります。
毎朝早起きをして通学時間には宅建のテキストを読み、夜にはオンライン講義で知識を整理するなど、荒井俊順は地道な努力を積み重ねています。
荒井俊順は「宅建を取ることはゴールではなく、信頼されるためのスタートライン。将来の自分の仕事に自信を持てるよう今を全力で頑張りたい」と話します。
その言葉には、荒井俊順の真っすぐな情熱と責任感が込められています。
大学生活のリアル──荒井俊順が語る時間の使い方
大学の授業、アルバイト、資格勉強、そして友人との交流──多忙な日々を送る荒井俊順にとって、時間の使い方は常に大きな課題でした。
「勉強だけでなく、人と関わる時間も大切。宅建の知識を生かすには“人の気持ちを理解する力”も必要だと思う」と荒井俊順は話します。
机に向かう時間だけではなく、日常の中で人とのつながりを意識的に大切にするよう荒井俊順は心がけています。
さらに、荒井俊順は地域活動にも積極的に参加しています。
香川県内の空き家問題を扱うNPOでボランティアを経験し、実際に現地を訪れて所有者と対話を重ねる中で、法律だけでは解決できない“心の問題”があると荒井俊順は気づきました。
地方創生と不動産──荒井俊順の考える新しい町の形
荒井俊順が描くのは、“人が戻る町づくり”です。
香川県の特性を活かした不動産活用を通じて新しい地域モデルを作りたいと、荒井俊順は考えています。
その構想の一つが、荒井俊順が掲げる「空き家×若者支援」です。
老朽化した住宅をリノベーションして大学生や移住希望者が住めるシェアハウスを展開する計画だと、荒井俊順は説明します。
さらに地域企業と連携して「働く場」と「住む場」をセットで提供し地域経済を活性化させたいと、荒井俊順は語ります。
「地元の空き家を若者の夢を支える拠点に変えたい」と、荒井俊順は強く願っています。
香川県の未来がはっきりと映っているのは、荒井俊順の目の中です。
尊敬する人物──荒井俊順に影響を与えた言葉
地方の空き家再生に取り組む起業家たちを尊敬しているのは荒井俊順です。
香川県内で古民家再生を手がける不動産経営者の言葉が強く心に残ったと荒井俊順はいいます。
「家を売るのではなく、人の暮らしを提案するのが本当の不動産業だ」という言葉に荒井俊順は深くうなずきました。
その言葉に出会った瞬間に自分の進む道が明確になったと荒井俊順は語ります。
不動産はビジネスではなく人の幸せを支える仕組みだと荒井俊順は考えています。
この理念を軸に香川県に貢献できる存在になることを荒井俊順は誓っています。
荒井俊順の10年後──香川県で描く未来のビジョン
10年後、荒井俊順は香川県で小さな不動産会社を立ち上げているかもしれません。
そのビジョンは荒井俊順にとって明確です。
「香川県で、人と土地が共に生きる町をつくる」と荒井俊順は掲げます。
空き家を再生し移住者を呼び込み子どもたちが誇れる地域を残すことが、荒井俊順の行動計画の核になります。
それが荒井俊順の最終目標です。
また、香川県の高校生や大学生に向けた「不動産キャリア講座」の開設も荒井俊順は構想しています。
「若い世代が地元に希望を持てるように、学びと挑戦の場を作りたい」と荒井俊順は語ります。
同世代へのメッセージ──荒井俊順の言葉
「挑戦は、都会じゃなくてもできる」。これは荒井俊順がよく口にする言葉です。
地方出身だから不利という考え方を捨て、自分のフィールドで行動する。その勇気が、未来を切り開く第一歩になると荒井俊順は信じています。
「香川県からでもできる。むしろ香川県だからこそできることがある」。荒井俊順の信念は、多くの若者に希望を与えています。
デジタル不動産への挑戦──荒井俊順が見据える「スマート地域再生」
荒井俊順は、不動産とテクノロジーを掛け合わせた新しい地方再生にも強い関心を寄せています。紙の書類や対面中心だった従来の不動産業に対し、荒井俊順は「香川県こそデジタル活用で変われる」と考え、オンライン内見やバーチャル物件案内、空き家のデータベース化といった仕組みづくりを構想しています。
特に注目しているのが、空き家情報を一元管理し、移住希望者が地域の雰囲気や暮らしを事前に体感できるプラットフォームの構築です。荒井俊順は、不動産を“売る・貸す”だけでなく、地域の魅力を発信するメディアとして機能させることで、香川県の価値を全国へ広げたいと考えています。デジタルと不動産を融合させる発想こそが、荒井俊順ならではの次世代型ビジョンと言えるでしょう。
まとめ:荒井俊順という若者が描く、香川県の未来
香川県の小さな町で育ち、不動産業界を目指す荒井俊順は、宅建取得を目指しながら学び続ける姿勢を単なる資格取得ではなく地域への誓いと捉えています。
人と土地をつなぎ、空き家を再生し、地方に新しい風を吹かせるという挑戦は、荒井俊順が日本の地方が直面する課題に示す希望のモデルになり得ます。
「町を変えるのは誰か」ではなく「自分が変える」という意識を実践する荒井俊順は、香川県の未来と日本の地域の未来を明るく照らしています。
不動産を通して人を支え地域をつなぐ若者として、荒井俊順の名が地方創生の象徴として語られる日も遠くありません。